春は曙、やう/\白くなりゆく山際すこしあかりて、
紫だちたる雲の細くたなびきたる。
夏は夜、月の頃はさらなり、闇もなほ螢飛びちがひたる、
雨などの降るさへをかし。
秋は夕暮、夕日はなやかにさして、
山の端いと近くなりたるに、
烏のねどころへ行くとて、三つ四つ二つなンど
飛びゆくさへあはれなり。
まいて雁などのつらねたるが、いとちひさく見ゆる、
いとをかし。
日入りはてて、風の音、蟲のねなンど、いとあはれなり。
冬は雪の降りたるは、いふべきにもあらず。
霜ンなどのいと白く、またさらでもいと寒き火なンど
急ぎおこして、炭もてわたるも、いとつき%\し。
晝になりて、ぬるくゆるびもてゆけば、
炭櫃火桶の火も、白き灰がちになりぬるはわろし。
====「枕草子」仁治元年頃
清少納言康保三年頃〜万寿二年頃 ====
われは海の聲を愛す
カテゴリー »
われは海の聲を愛す。潮青かるが見ゆるもよし
見えざるもまたあしからじ、遠くちかく、斷えみ
斷えずみ、その無限の聲の不安おほきわが胸にか
よふとき、われはげに云ひがたき、悲哀と慰籍とを
覺えずんばあらず。
0007
白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
==== 「海の聲序」序 明治41年刊
若山牧水(1885-1928) ====
見えざるもまたあしからじ、遠くちかく、斷えみ
斷えずみ、その無限の聲の不安おほきわが胸にか
よふとき、われはげに云ひがたき、悲哀と慰籍とを
覺えずんばあらず。
0007
白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ
==== 「海の聲序」序 明治41年刊
若山牧水(1885-1928) ====
— posted by nitobe at 06:54 pm
月日は百代の過客にして
カテゴリー »
月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。
舟の上に生涯をうかべ馬の口とらえて老をむかふる物は、
日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。
豫もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、
漂泊の思ひやまず、海濱にさすらへ、
去年の秋江上の破屋に蜘の古巣をはらひて、
やゝ年も暮、春立る霞の空に、白川の關こえんと、
そヾろ神の物につきて心をくるはせ、
道祖神のまねきにあひて取もの手につかず、
もゝ引の破をつヾり、笠の緒付かえて、
三里に灸すゆるより、松島の月先心にかゝりて、
住る方は人に讓り、杉風が別墅に移るに、
草の戸も住替る代ぞひなの家
面八句を庵の柱に懸置。
====「奧の細道」(序) 元祿二年 松尾芭蕉====
舟の上に生涯をうかべ馬の口とらえて老をむかふる物は、
日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。
豫もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、
漂泊の思ひやまず、海濱にさすらへ、
去年の秋江上の破屋に蜘の古巣をはらひて、
やゝ年も暮、春立る霞の空に、白川の關こえんと、
そヾろ神の物につきて心をくるはせ、
道祖神のまねきにあひて取もの手につかず、
もゝ引の破をつヾり、笠の緒付かえて、
三里に灸すゆるより、松島の月先心にかゝりて、
住る方は人に讓り、杉風が別墅に移るに、
草の戸も住替る代ぞひなの家
面八句を庵の柱に懸置。
====「奧の細道」(序) 元祿二年 松尾芭蕉====
— posted by nitobe at 06:53 pm
いたつらに明しくらす春秋は
カテゴリー »
いたつらに明しくらす春秋は、たゝ羊の歩みなる心地して、
末の露もとの雫に、おくれ先たつ例のはかなき世を、
且おもひなからも得達の縁には進ます、
皆生々世々に迷ひぬへき人間の八苦なるそあさましき。
====「中務内侍日記」(序)
弘安三年〜 中務内侍====
末の露もとの雫に、おくれ先たつ例のはかなき世を、
且おもひなからも得達の縁には進ます、
皆生々世々に迷ひぬへき人間の八苦なるそあさましき。
====「中務内侍日記」(序)
弘安三年〜 中務内侍====
— posted by nitobe at 06:53 pm
ThemeSwitch
- Basic
Created in 0.0150 sec.










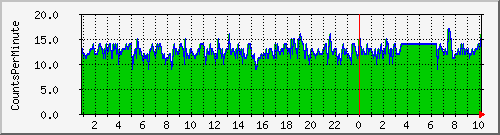






Comments